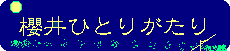「悲翠」
男は一年半ぶりに我が家に帰ってきた。妻は喜びの涙で夫をむかえた。彼は、都の寺の創建工事にかりだされていたのだ。
「おれたち田舎ものは、都の連中にいじめられっぱなしだ。自分だって、木を扱わせりゃ奴等にひけをとらないはずなのに、朝から晩まで物運びしかやらせてもらえなかった。気がめいってよそごとばかり考えていたら、柱材の載る大力車をよけそこなってしまって」と男は、右膝からくるぶしにはしる傷痕をしめした。
「あえなくお役ごめんとなったが、これじゃ歩いて帰れやしない。傷の癒えるのが、本当に待ち遠しかったよ」
男はそれっきり、都での出来事を語ろうとしなかった。
幼い息子ふたりは、最初こそ戸惑い気味の表情で男の頬擦りを受けていたけれど、二日も経つと、しぜん父の膝の上を争いはじめた。
時は新緑の季節で、せまい盆地の村はまぶしい若葉の照りかえしに充ちていた。卯の花垣にかこまれた庭で、男は器用に丸太を削りつづけた。子どもたちは、切粉のとどかないところから、手斧や鑿をあやつる父の手つきを見守っていた。
彫りの済んだ丸太にほぞ穴と溝を入れ、そこに厚い樫板を差しこむと、高さ二尺ほどの木馬ができあがった。待ちかねていた兄弟は、その背中にふたり乗りでまたがった。
はしゃぐ我が子を間近に見ながら、軒端に立つ妻の顔つきは浮かなかった。ふたりの声が高まるほど、彼女の眉間にさす翳は濃さを増した。
やがて兄弟が、「おうまにのってみやこへゆこ」と唄いはじめた。女は堪えかねたように水桶を持ち、足早に裏の沢へ向かった。
板戸の透き間から洩る月の明かりが、見ひらいた女のまなこを照らしていた。
寝返りついでに男がふと目を覚ました。となりの妻が起きていることに気づき、「どうした、寝られないのか」と声をかけた。女は上を向いたまま「ええ」と答えた。
「今朝から元気がないな。どこか具合が悪いように見えるが」
「すこし火照りが」
「子どもは明日の川遊びを楽しみにしてるが、おまえは控えておくか」
「いえ、女にはつきもののことですから」
「そうか。でも無理はするなよ」
そう言って男は寝返りをうった。なおもしばらく、女は真っ暗な屋根裏を見あげていた。
翌日、近くの川へと通じる道を四人は歩いた。男は両脇に子どもをしたがえ、数歩遅れて歩く女は、跛をひく夫の右脚に視線をそそいでいた。
川原に降り立つやいなや、兄弟は浅瀬に走りこんだ。水の冷たさなど気にかけず、掬んだ手で撒き上げるしぶきの高さをきそいあった。
「着物を濡らすと風邪が起こりますよ」
母に注意され、兄弟はしぶしぶ岸にあがった。上の子がすこし離れた岩場を指差した。
「水に入らないから、あそこに行ってもいい?」
「いいけど、気をつけて遊ぶのよ」
「はい」
ツツジの子株をまたぎ、兄弟は岩づたいに歩きはじめた。そのあとを追おうとする夫の袖を、女の手が引き留めた。
「遊びなれた場所です。心配はいりません」
「だからといって、おれが行っちゃいけないことはないだろう」
不満を露わにした夫から、女は顔をそらした。
「子ども同士の遊びも大切ですから。・・・・・・それより、あなたに訊きたいことがあります」
「何だ。妙にあらたまって」
「これからもここに留まるおつもりですか。それとも、いずれ都に戻るおつもりでしょうか」
「どうして、そんなことを言い出すんだ」
夫は平然と問いかえした。
「行李の中に、まだ解かれていない衣装包みがあるでしょう」
「そりゃ、ふたたび仕事にありついたときのためだ」
「都に住んだら、ずいぶん用意がよくなりましたね。それもあの方のおかげですか」
「おい、いいかげんなことを言うな」これにはさすがに、男も狼狽の色を示した。けれど女は夫を見返ることなく、落ち着いた口調を保ちつづけた。
「着物の用意はしつけられても、寝言のくせは矯められなかったみたいですね。おとといの明け方、聞いてしまったんです。わたしではない人の名前と、苦しそうに謝るあなたの声を。・・・・・・どうぞ教えてください、その方がどんな女の人か」
波紋に融けた陽ざしが、女の横顔に淡い翳をおどらせた。どこから飛んできたのか、川中に突き出た木の枝に一羽のカワセミが舞いおりた。羽根の翠が若葉の緑をしのぎ、周囲に虹色の余光をめぐらした。その色からきっかけをつかんだように、男が口をひらいた。
「人足小屋のまかないをやっていた女だ。傷を負ってから歩けるまで、すべて身の回りの世話を焼いてくれた」
「せまいところで人目もあったでしょうに」
「いや、働けないと分かれば、もう人足のいる場所には置いてもらえない。あいにく施療院もいっぱいで、その女の情けにすがるより生きる手だてはなかった。向こうも数年前に婿を亡くし、おっ母さんとふたり住まいという身ゆえ、ひそかに男手をもとめていたらしい。なるほど住まいの壁はやぶれ放題、屋根は雨漏りし放題だ。傷が癒えてからそこいらじゅうを直してやった」
「お母さんは何も?」
「すなおに喜んでくれたよ。なにしろ自分も咳病もちで、床に臥せりがちな日を送ってるんだ。その病状も春をさかいに落ち着いてきたんで、おまえたちの元に帰り、すべてに決心をつける気になったという訳だ」
女はややうつむいて考えるそぶりを見せた。水中の魚影をうかがうカワセミの姿を、ちらりと上目でたしかめ、彼女はまた額をあげた。
「決心など、もうついているではありませんか」
「どういうことだ」
「あなたはふたたび都にのぼるでしょう」
「なぜ、そう言いきれる。この命よりおまえたちをいとおしむ、おれの気持ちが分からないのか」
「分かっているからこそ、その方の待つ都に戻ると言うのです」
「意地わるく責めるのはやめてくれ。おれだって鬼じゃないんだ。暮しに困っている恩人を、簡単に袖にすることはできなかった。でも心の底ではずっとおまえたちのことを想っていたよ。でなきゃ、ここでいま肩を並べて立っていることもありえない」
「それならなぜ、つらい大雪の頃に帰ってきてくださらなかったのです。こちらの寒さは、都よりきびしくてあたりまえ。食べるものだって、正月前に櫃の底が覗けるほど窮していたのです。遠く離れていようとも、薄い粥をすすり、すきま風に震えるわたしたちの姿が、あなたのまなこに映らなかったはずはありません。なのにどうして、この暖かくわずらいのない季節まで待つことができたのでしょう。そう、わたしではない人の幸せを、あなたがより重く考えていたためです」
「だから、向こうのおっ母さんの具合が悪くて・・・・・・」
「いいんです。別にあなたはなまけていた訳ではなく、本当につらい季節を他の人のため過ごしただけですから。そのときすでに、あなたの心は決まっていたのでしょう」
「そんなことはない、そんなことはない」くちびるを震わしながらつぶやく男が、ふと妻の肩ごしに息子たちのいる岩場をのぞんだ。すると、小さなふたりが助け合い、大岩を乗りこえる様子が目に入った。
男は急に涙ぐんだ。そしてついに観念したように、「すまん、本当にすまん」と頭を垂れた。
「いえ、こうして帰ってきてくださったおかげで、楽しい夢を見ることができました。あなたには感謝しています。しかし女は、あなたがた男と違い、夢を追うだけで生きてはゆけないのです。やがては覚める夢ならば、かえって見ないほうがまし。きっと都の方も、同じ想いであなたを待ちわびているでしょう。早く戻ってさしあげなさい」
女は夫と向き合った。男はおもてを伏せたまま、「すまん」の文句をくりかえした。
「ねえ、こっちにきて。オタマがいっぱいいるよ」
岩場からひょいと顔を出し、上の子が叫んだ。
「いま行くから待ってて」と応え、女はわざとゆっくりした動作でツツジの株をよけた。そのまま横顔で、彼女は夫に出立をうながした。
「今ならあの子たちも気づきません。家に帰って荷物をまとめ、すぐに村を立去ってください。それでは、いつまでもつつがなく」
何度も妻子の様子を振りかえりながら、男は土手の坂をのぼっていった。その姿が竹林の陰にかくれたとき、川中のカワセミも枝をはなれた。濃い翡翠の矢が水面をかすめて飛び去ると、景色はいっしゅん真冬のような閑寂のうちに色をひそめた。
了
|